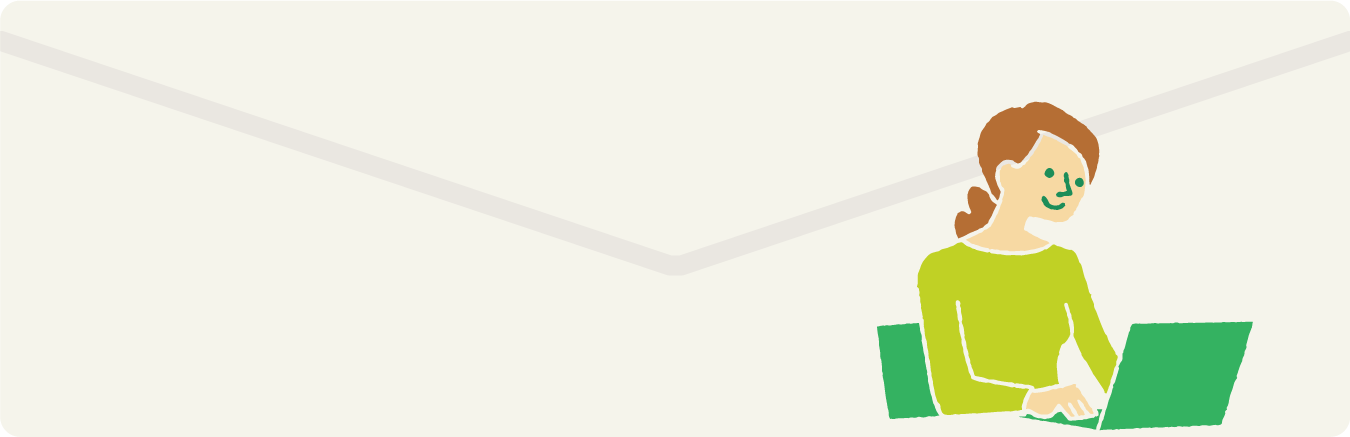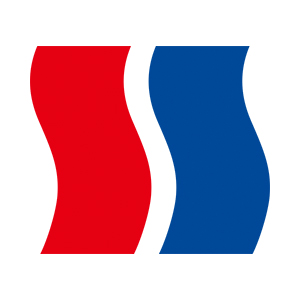ポイ捨てのない社会へ。グリーンバードの目指す未来
福田さんは、環境問題についてどのようなお考えがありますか?

「もう他人事じゃない」と強く感じています。もともと環境問題に関心が高かったわけではありませんが、グリーンバードの活動を通じて現状を知り、その深刻さを痛感しました。
特に、ゴミの最終処分場である埋立地が、あと20年ほどで満杯になってしまうと言われていることには大きな危機感を覚えています。 僕たちは日々ゴミ拾いをしているからこそ、現代の大量生産・大量廃棄の問題について、より深く考えなければならないと思っています。
そのために、参加してくれる人たちに対しても、少しずつ環境問題の現状を伝えていきたいと考えています。 例えば「今日拾ったゴミの約8割は海に流れ着いている」とか「なぜ分別が必要なのか」といったことを知るだけでも、意識が変わるきっかけになるかもしれません。
たとえ「仕方なく」始めたゴミ拾いだったとしても、活動を通じて「誰かにこの話をしてみたいな」「環境問題について、もう一歩考えてみようかな」と思ってもらえたら、それだけでも嬉しいですね。
世の中の環境問題への関心について、実際に活動をしていて変化を感じることはありますか?

世の中の変化をとても感じています。テレビやメディアを見ていても、環境問題やSDGsに触れない日はないくらい、頻繁に取り上げられていますよね。実際、教育現場や企業でも、環境教育やCSR活動に積極的に取り組むところが増えてきました。
5〜10年程前は「とりあえず企業としてサステナブルな活動をしないといけないので、ゴミ拾いをしよう」という消極的な姿勢の企業が多かったですが、今は少し変わってきています。 SDGsやCSRを担当する企業の方々も、もともと環境の専門家ではないことがほとんどですが、環境団体の話を聞いたり、現場に足を運んだりしながら、知識と理解を深めた上で活動するようになっていますね。
グリーンバードとしても、こうした意識の変化を後押しし、より多くの人が気軽に環境問題に関われるような場を作っていきたいですね。
活動を通じて感じる環境問題や、それを踏まえて普段の生活の中で気をつけていることはありますか?

気をつけているというより、それがもう日常の一部になっているのかもしれません。 レジ袋をもらわない、水筒や給水スポットを活用する。特別に「エコな活動をしているぞ!」という意識はなくて、むしろその方がシンプルに節約にもなりますよね。
環境のためにやろうと押し付けるのではなく、おしゃれだから使うとか、安くなるからやるとか、そんな理由でいいと思うんです。 ゴミを拾ったからといって温暖化が止まるわけではないけれど、1人ひとりの小さな行動が、結果的に地球の延命措置にはつながるのかなと。
僕たちグリーンバードのゴミ拾いも「環境のために頑張ろう」というよりは「ちょっといいことしてみよう」くらいの気持ちで、気軽に参加してもらえたら嬉しいですね。
最後に、グリーンバードを今後どのような団体にしていきたいですか?

グリーンバードの最終目標は「ポイ捨てのない社会」の実現です。
そのために、より多くの人にゴミ拾いや僕たちの活動に関わってもらいたいと思っています。
実際、この20年間で多くの企業や学生、団体とのつながりが生まれ、それが東京だけでなく全国に広がってきました。 僕たちはさらに多くの人を巻き込みながら、ゴミ拾いの活動を広げていくハブのような存在になりたいんです。
これからはNPOとしてそのつながりをさらに強化し、僕たちがその中心となることが求められていると思います。
企業と自治体、住民と企業、若者と行政など、普段交わることの少ない人たちをつなぐ存在になりたい。
そして、それをつなぐためのコミュニケーションツールが、僕たちにとって「ゴミ拾い」なのかもしれません。
編集後記
今回、NPO法人グリーンバードの理事長 福田圭祐さんにお話を伺い、単なる「ゴミ拾い活動」ではない、そこに込められた理念や工夫に驚かされました。
実際に私もゴミ拾い活動に参加しましたが、学生や社会人、海外からの留学生、そして10年以上続けているベテランの方まで、さまざまな人が集まっていました。 そんな多様な人々が自然と会話を楽しみながら街をきれいにしている姿が、とても印象的でした。
「グリーンバードの目的は、ゴミ拾いではなく「ポイ捨てのない社会」をつくること。そのために、誰もが気軽に楽しく参加できる仕組みを工夫しています。
「ちょっといいことをしてみよう」と始めた行動が、新しいつながりや価値を生み、社会や環境への意識を広げていく。そんなポジティブな循環こそが、グリーンバードの魅力だと感じました。
この記事を通じて、少しでも「自分も何かできるかも」と思うきっかけになれば嬉しいです。