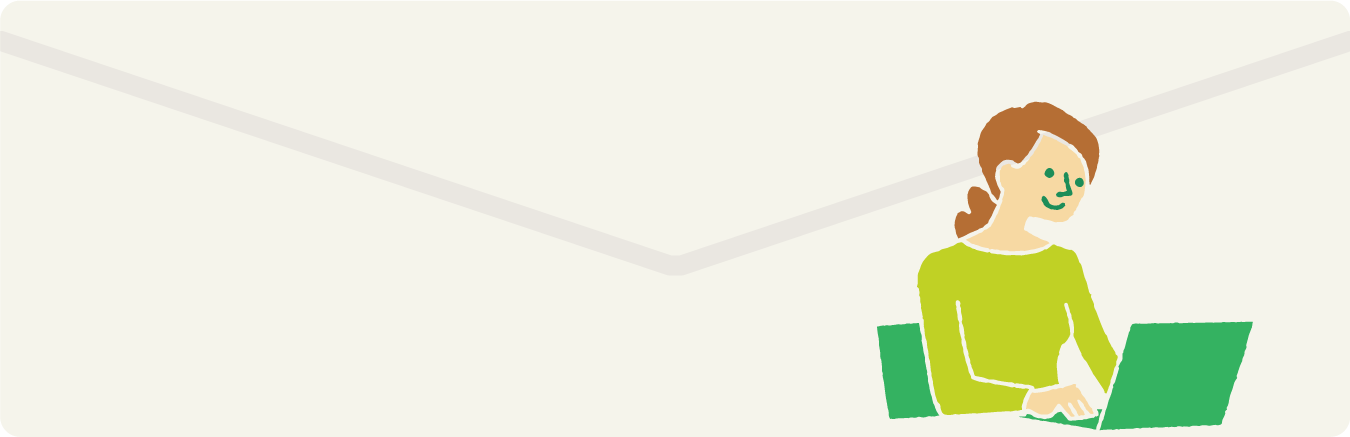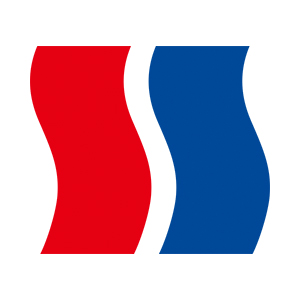地球温暖化や海洋汚染、森林破壊など、私たちの住む地球には問題が山積みです。 このままの状態が続くと、人間も動物も安全に暮らせなくなってしまいます。
地球環境の悪化に歯止めをかけるためには、地球で暮らす私たちの心掛けが大切です。 一人ひとりが毎日の生活の中で「エコ」を意識すれば、次第に地球全体にポジティブな影響を及ぼすでしょう。
エコ生活を心がけて、皆で明日の地球をつくっていきましょう。
エコ生活とは?

豊かな地球環境を守るために大切なのが、一人ひとりの心掛けです。
無理なくできることから、少しずつ。
いつもの「生活」から「エコ生活」に切り替えて、未来を変えていきましょう。
ここではエコ生活の例を3種類ご紹介いたします。
ごみを削減する
食品ロスやプラスチックごみの問題など、増え続けるごみの量が地球環境に負荷をかけ世界的に問題になっています。たとえば、衣類はリサイクルショップに持っていったり、ごみをきちんと分別し資源にまわすなど、リサイクルを意識したエコ生活をしましょう。また、プラスチックごみ削減のためエコバッグを持ち歩いたり、食品ロス削減のため食料品は必要な分だけを購入するなど、こまめなエコを習慣化することでごみは減らすことができます。
節電する
地球温暖化の原因は、有害物質や温室効果ガスによるものといわれています。
温室効果ガスの1つである二酸化炭素を私たちが日々の生活の中で少しでも減らすよう意識すれば、地球の環境は少しずつ変わっていくはずです。私たちの生活に密接に関わるもので二酸化炭素を生み出すことに繋がっているのが電気です。多くの人が節電を意識し、電気を必要以上に使いすぎないよう心がけることで、二酸化炭素排出量の減少に繋がっていくでしょう。
また、太陽光発電などの再生可能エネルギーは、発電時も利用時も二酸化炭素をほぼ排出しないため地球にやさしいエネルギー源として注目されています。
現代では多くの電力会社が再生可能エネルギーを電源としたプランを用意しているので、今使っている電力会社のプランを調べ、可能であれば再生可能エネルギーを家庭でも取り入れてみましょう。
資源を大切にする
木材、水、化石燃料などの資源は、私たちの暮らしに欠かせません。
しかし、これらは限りあるものです。日ごろから使い捨ての商品ではなく継続して使えるサステナブルな商品を選ぶなど、ごみを減らすよう意識したり、無駄なエネルギー消費を避け省エネを心がけたりなど、資源を大切にしましょう。
たとえば、マイ箸を持ち歩けば割り箸ごみの削減になりますし、タンブラーや水筒などを持ち歩けばごみになるペットボトルや紙コップの削減になります。無駄な電気を消して節電、水を流しっぱなしにしないなどの節水もエコ生活の基本ですね。
また、不要になったものは売ったり、他のアイテムにリメイクしたり、リサイクルを意識した生活もポイント。近所への外出の際は車ではなく徒歩や自転車を選べば、化石燃料の消費削減や二酸化炭素排出量を減らすエコな取り組みになります。
このように、地球環境保護のためにエコ生活を習慣化していきましょう。
エコ活動が注目されている理由

エコ生活・エコ活動が世界的に注目されている背景には、以下のような環境問題があるのをご存じですか?
私たちの快適で豊かな暮らしと引き換えに、地球は悲鳴をあげているのです。
これらの環境問題を放置すると、そのうち快適で豊かな暮らしが失われるだけでなく、次の世代が生きる時代に大きな課題を残してしまうことを大人は考えていかないといけません。
地球温暖化
いま「地球温暖化」は世界的に大きな問題となっています。
2021年に発表されたIPCC第6次評価報告書では、2011年~2020年の世界平均気温が産業革命前(1850年~1900年)の平均気温と比べて約1.09℃上昇したと報告されています。さらに、2024年には世界の平均気温が産業革命前より1.5℃高くなり、観測史上最も高い年となりました。これらのデータは、地球温暖化が進行していることを示しています。
地球温暖化の原因は、温室効果ガス。人間の活動によって大量の温室効果ガスが発生し、それが地球の温度を全体的に上げているのです。本来、地球の表面にある二酸化炭素や酸素などの大気が、太陽から放出される熱により温められた地球の温度を一定に保つ役割を果たしています。しかし、石油や石炭などを燃焼させて大量に消費することにより、二酸化炭素(CO2)を中心とした温室効果ガスが大気中に大量発生します。温室効果ガスの濃度が高まり宇宙に放出されない熱は、大気の内側にこもります。これが地球温暖化のメカニズムです。
昨今、日本でも集中豪雨や強い台風などの異常気象が確認されています。世界に目を向けても、熱波や干ばつなどが発生し、地球全体が温暖化の影響に悩まされている状態です。
地球温暖化がすすむと、気候や生態系が変化して、人間を含めて動植物が快適に暮らせなくなってしまいます。未来の世代により良い環境を残すため、私たち一人ひとりが「地球温暖化をストップさせるために何ができるのか」を考える必要があるでしょう。
\上がり続ける気温。いま地球は沸騰化している?!/
生活ごみの増加
世界的な人口増加にともない、排出される生活ごみの量も増えているのも大きな環境問題のひとつです。2020年には世界全体で約4億トンものプラスチックが生産され、その多くがリサイクルされず廃棄物となっています。その廃棄物は処理が追い付かず、集積されたまま放置されたり海へ流出し汚したりする例は少なくありません。
日本でも、3R(リユース、リデュース、リサイクル)が進められるのはもちろん、商品パッケージの簡易化や食品ロス対策などごみを減らす取り組みがすすめられています。今後も社会全体でさらなる工夫が求められるでしょう。
2019年のデータでは、世界で発生したプラスチックごみのうち、9%しかリサイクルされず、20%以上が不適切に処理され、約2,200万トンが海や陸地に流出しています。この増え続けるごみが海へ流出する海洋プラスチックごみも解決すべき問題のひとつです。
\街をきれいに!スポーツ感覚でごみ拾いを競い合ってみた/
プラスチックごみによる海洋汚染
石油由来のプラスチックは、他の自然由来のごみと異なり、微生物の働きで自然に還る生分解はされません。そのため、流出したプラスチックごみは数百年は残り続けると言われています。WWFジャパンの調査によれば、世界の海では1億5,000万トンのプラスチックごみが海に存在するそうです。さらに、現状のプラスチックごみに加えて、毎年800万トンのごみが海へ流出しています。2050年には海の中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算もあり、プラスチックごみによる海洋汚染は深刻な状況です。
海へたどり着いたプラスチックごみは、海洋生物にとって害でしかありません。魚やカメなどの海洋生物のほか海鳥などが誤って食べたり絡まったりして死亡する事例が相次いでおり、生態系への悪影響が懸念されています。
大きなごみはもちろんですが、海洋中で劣化し5mm以下になったマイクロプラスチックごみも問題視されています。マイクロプラスチックごみは、海中の有害化学物質(ダイオキシンやDDTなど)を吸着しやすい性質を持っています。小さいぶん海中を広い範囲で移動し、有害物質を遠くまで運びます。
研究では、魚がマイクロプラスチックを食べると、摂食障害や炎症反応を起こすことがわかりました。また、有害物質を蓄積した魚を人間が食べると、免疫力低下やガン、ホルモン異常などにつながるとも言われています。血管に入り込んだマイクロプラスチックが心臓発作や脳卒中、死亡のリスクを高めるという研究もあります。
海洋プラスチックごみを削減するため、世界や日本ではプラスチック使用抑制の動きが広がっています。
私たちもプラスチック製のレジ袋ではなくエコバックを使用したり、プラスチックストローではなく紙ストローを使用したりなど、プラスチックごみを出さない工夫や、万が一海に流出しても海中で自然に還る生分解性のある素材を選ぶなど、一人ひとりができることから始めていきましょう。
\海洋プラごみの量はどのくらい?クイズに答えてみよう!/
海面水位の上昇
地球温暖化により、海の氷が溶ける事例が多発しています。
氷が溶けて海に流れ込んだり、海水が温まって膨張することが原因で海面水位が上昇し、このままだと海抜の低い島や都市が水没すると言われています。また、それに伴い農地への浸水被害や海の生態系破壊なども懸念されます。
国土交通省の発表によると、2006年以降の世界の海面水位は、1年間に3.6mmずつ上昇しているそうです。
実は日本でも海面水位の上昇は進行しており1980年から2020年までの40年間でなんと8.7cm上昇していて、今後さらなる上昇が予測されています。2024年8月の国連報告書によると、2050年には大阪で2020年と比べ27cm上昇、東京では13cm上昇すると発表され、私たちにとって決して他人事ではない大きな問題となっています。
\海面上昇について、もっと掘り下げて学んでみよう!/
二酸化炭素排出量の増加
エアコンや車など、私たちの快適な生活には二酸化炭素(CO2)の排出がつきものです。
実際、二酸化炭素の排出量や濃度は年々増加しており、産業革命前よりも4割ほど増えているといわれています。今後暮らしがますます便利になるに従い、二酸化炭素の量もさらに増えていくでしょう。
近距離の外出であれば、車ではなく徒歩や自転車を使いましょう。二酸化炭素の排出抑制になるうえ、筋力がつくなど健康促進効果も期待できます。
\ママチャリ移動で排出CO2ゼロを実現!体当たりレポート/
森林の減少
森林の減少も、地球規模の環境問題のひとつとされています。農地等への土地利用転換や違法な大量伐採、森林火災などが森林減少の主な原因としてあげられます。
健全な森林を保つためには、適切な収穫をした後、植林をして苗木を育て、間伐を行い森を育てることが大切です。林業が衰退している今、森が荒れ地滑りや土砂崩れなどの災害も発生しています。大切に育てられた木は大切な限りある資源です。適切に使い利用するのはもちろんですが、再生紙を選んだり、森林認証マーク(FSCマーク/森林が適切に管理されている証明)のついた製品を選ぶことで限りある資源を大切に活用していきましょう。
また、大切な資源のひとつとなる古紙が今不足しているのをご存知ですか?使用後は古紙を資源回収に出し、リサイクルを意識しましょう。使わなくなった紙袋や包装紙をリメイクするなど、家庭でのリサイクル活動もおすすめです。まずは、自分の身近なところから始める取り組みは森林保護になるうえ、手作業でつくった製品なら愛着も湧くので大切ない長く利用することがエコな生活にもつながります。
\大人気コンテンツ!家庭に眠る紙袋でつくってみよう/
生態系の破壊
自然界では、多種多様な生物が互いに影響し合いながら存在しているため、地球温暖化や海洋汚染など地球規模の変化があると、影響を受ける生きものが増えます。
ある特定の生きもの1種に影響が出ると、他の種にも影響が及び、連鎖的に飢餓・絶滅の危機に瀕してしまうのです。
WWFジャパンによれば、絶滅の危険性が高い種(絶滅危惧種)に挙げられる生物は年々増えており、2000年時点では10種あまりだったその数が、2020年には4,000種、2024年時点では7,400種にものぼっているそうです。
動植物は、与えられた環境の中で生きるしかありません。
私たち人間が、エコな暮らしを心がけて、すべての命が快適に過ごせるような地球をつくりましょう。
\生物多様性の損失を止めろ!1分で学んでみよう/
エコ活動で得られる暮らしのメリット

地球環境の保全に、一人ひとりのエコ活動は欠かせません。
しかしエコ活動のメリットはそれだけではなく、巡りめぐって私たちの暮らしにもポジティブな影響を及ぼします。
エコ活動の効果を知れば、ますます興味深く取り組めそうですね。
健康な体づくりができる
エコ活動の中には、体づくりに関するものもあります。
たとえば外出時に車ではなく徒歩や自転車を選べば、運動不足の解消や筋力アップが期待できるでしょう。
二酸化炭素排出抑制のための活動が、自分のためにもなるなんて、やらない手はありませんね。
家計を節約できる
節電・節水もエコ活動のひとつなので、毎日続けると結果的に家計の節約につながります。
「こまめに電気を消したら今月の電気代が安くなった」というように、数字で結果が見られるので、続けるモチベーションにもなります。
また「食べる分だけ購入する」を意識すると、余計なお金がかからなくなるうえ、食品ロス削減も実現できます。
食品を買う際は賞味期限に十分注意しましょう。どうしても余りそうな食材があったら、フードバンクや子ども食堂に寄付すると無駄がなくなります。
環境問題に興味が湧く
「エコ活動を始めたことが環境問題について考えるきっかけになった」という方は珍しくありません。
お子さんがいる方なら、環境問題に興味を持つきっかけになりそうです。話の入口として、世界や日本が抱える問題やSDGsについて教えてあげてください。
エコ活動が習慣化すれば、普段から環境に配慮した行動ができるでしょう。
今日からできるエコ活の取り組み事例

私たち一人ひとりがエコを意識すれば、次第に地球環境はポジティブに変わっていきます。
毎日の生活の、ちょっとしたひと工夫。
エコ生活を実現するために、「家庭でできる取り組み例」「子どもができる取り組み例」「企業ができる取り組み例」の3パターンを見ていきましょう。
家庭でできる取り組み事例
まずは家庭でできる取り組み例から紹介します。
家族で「今日はこんなエコ活動をしたよ」と報告し合うのも楽しそうですね。
リビング編
家族だんらんのメイン場所であるリビングでは、「電気」を意識するのがポイントです。
たとえば、使わない電化製品はコンセントを抜いたり、テレビを誰も見ていなければ消したり、使っていない照明はオフにしたりなど、こまめな節電はエコにつながります。
また、エアコンの設定温度を見直したり(夏は冷房28℃、冬は暖房20℃が理想)、契約中の電気料金プランや電力会社を見直したりするのも良いですね。
キッチン編
キッチンは、家族の食事をつくる大事な場所です。
水、ガス、電気などあらゆるものを使うので、節水・節電を意識しましょう。
冷蔵庫でいうと、冷蔵庫の設定温度を季節によって変えたり(夏は「強」、冬は「中」にするなど)、冷蔵庫の中にモノを詰め込みすぎないようにしたりするだけでエコになります。
設置場所も、壁から離して放熱スペースをつくってください。
料理家電でも、電力を使った保温をできるだけ短めにしたり、野菜の下ごしらえは電子レンジを活用したり、ガスの炎が鍋底からはみ出していないか注意したりなど、できることがたくさんあります。
節水面では、水をこまめに止めるのはもちろん、鍋の汚れはできるだけ拭き取ってから洗うようにしましょう。エコにつながるだけではなく、排水が少なくなることで家計の助けにもなります。
食事編
食事において「食品ロス」は喫緊の課題です。
「食品ロス」とはまだ食べられる食べ物を捨ててしまうことをいいます。2022年度には、国民1人につき年間38kg、日本全体で年間472万トンの食品ロスを発生させています。
食べ物を捨ててしまうことで、食材を焼却するときに発生する二酸化炭素が問題になっています。
また、世界では焼却ではなく埋め立てでの対処が主流ですが、食材が分解されるときに発生するメタンガスは二酸化炭素の25倍の温室効果があるとされています。つまり食品ロス問題を通して、世界中で毎日のように地球温暖化を加速させている状態なのです。
食品ロス問題の解決は、決して難しいことではありません。
嫌いな食材でも食べたり、食べられる分だけをつくったりなど、食事を残さないように工夫しましょう。また外出時は持ち帰り可能な店を選ぶことをおすすめします。
「どうしても食材が余ってしまった」という場合は、レシピサイトを検索すれば有効活用のアイデアが見つかるかもしれません。味付けなどを工夫して、おいしく消費してください。
また全国的にフードドライブの取り組みもすすめられています。余った贈答品や食品は、専用ボックスに入れて子ども食堂などに寄付しましょう。
トイレ編
トイレでのエコ活動は、家庭だけではなく外出先でもできます。
自宅であれば、便座の暖房が不要ならオフにしたり、便座の暖房をつけているなら便座にフタをしたりするだけでもエコになります。
また、再生紙のトイレットペーパーを選ぶのも良いですね。
外出先では、手洗いの後はペーパータオルではなく、持参したハンカチなどを使いましょう。
買い物編
買い物の際は、商品の選び方を工夫しましょう。
エコバッグやマイカゴを持ち歩いたり、ばら売り袋詰めなど包装の少ない商品を選んだり、詰め替え品を購入したりなど、エコのために小さなことから続けていきましょう。
また、環境ラベルのついた商品を選ぶのもおすすめです。「エコマーク(環境負荷が少ない証明)」、「MSCマーク(海洋環境を守った漁獲方法の証明)」など、商品が作られた過程を確認してから選べると良いですね。
お風呂編
大量の水を使うお風呂では、主に水とガスの削減を意識しましょう。
シャワーはこまめに止めたり、追い炊き回数はできるだけ少なめにしたり(家族が連続して入るなど)、入浴していないときはお風呂にフタをしたりなど、小さなことでも続ければ大きなエコになります。
また、残り湯を流さずに洗濯に使ってみるのはいかがでしょうか?。エコ活動としてはもちろん、水道代が節約できるのもポイントで、温かさが残っている40度前後のお湯であれば、洗浄力の向上も期待できるようです。
自動車編
昨今、「エコドライブ」が推奨されています。エコドライブとは、燃料消費量やCO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけのことを指します。エコ活動のひとつとして、ゆったりと安全運転を意識してください。
発進から5秒間は時速20kmを保つことを目安とし急発進をしないこと、早めにアクセルを離してエンジンブレーキをうまく使い急ブレーキをかけないことは、エコ活動としてはもちろんですが、安全運転の基本でもあります。急な加速や減速を極力減らし、安定した運転を心がけましょう。
二酸化炭素排出抑制のため、無駄なアイドリングや無駄な空調は避けてください。
また、定期的にタイヤの空気圧をチェックしたり不要な荷物を下ろしたりすると、エコ走行が実現できます。
また、移動距離によっては「スマートムーブ」を意識し、自動車以外の選択肢も取り入れてみてください。
外出先編
外出先でも、エコのためにできることはたくさんあります。
まずは、一人ひとりが行動・習慣を変えていきましょう。
エコバッグやマイカゴ、マイ箸やマイボトルなど、自前のアイテムの持ち歩きはごみ削減につながります。
また、飲み終えたペットボトルや着なくなった服、不要になった紙資源などは、可燃ごみに捨てるのではなくリサイクルしましょう。
また、食品ロス対策として食料品は必要な分だけを購入し、外食時はできるだけ残さないよう意識してください。
子どもができる取り組み事例
次は、子どもができる取り組み事例を紹介します。
幼いうちからエコを意識することで、資源を大切にする大人へと成長するでしょう。
水を大切にする
お子さんが石けんを手で泡立てている間、水を出しっぱなしにしていませんか?
「水道をひねれば水が出る」は当たり前のことではなく、限りある資源を共有していることを伝えましょう。
節水が習慣化できれば、環境に対する意識そのものが変わりそうです。
環境問題を学ぶ
今地球がどのような状態に置かれているのか、地球を守るために私たちに何ができるのか、親子で環境問題を学んでみませんか。
お子さんの興味を惹くため、最初はテレビやYouTubeを活用するのも良いかもしれません。高学年のお子さんなら、インターネットや図書館で調べる方法もあります。
環境問題について学習したら、親子で「私はこう思う」「こうしたら良いのではないか」とぜひ話し合い、さらに興味・理解を深めるきっかけにしてください。
エコイベントに参加する
ワークショップや子ども向けセミナー、地域のごみ拾いなど、エコ関連のイベントに親子で参加するのもおすすめです。
環境に対する責任感を育めば、エコ活動を習慣化するきっかけになるでしょう。
\子どもたちの創造性にまかせて工作を楽しんでエコを実践しよう/
企業ができる取り組み事例
現在、さまざまな企業がエコ活動に参入しています。
環境保護はもちろん、業務効率アップ、コスト削減など社内でのメリットも実感できるでしょう。
残業時間の削減
従業員の残業時間を少なくするために、ノー残業デーや残業の事前申請制度を設ける企業は珍しくありません。早めに退社すると、エアコンやガスの使用量も減りCO2削減に。また従業員のプライベートも充実するので、モチベーションや業務効率にも良い影響が及ぶでしょう。
ペーパーレス化
少し前まで、企業が使う書類は紙が主流でした。
しかし、最近ではPDFなどの活用により、紙資源が使われなくなってきています。紙を使うことは材料である木材の循環を促し、森林の循環を促すことに繋がりますが、それでも紙の無駄遣いは無駄に天然資源を使うことに変わりありません。
無駄な紙の使用量を削減することで、書類を探す時間削減、紙代削減、書類の保管スペース削減、インク代削減など、地球にも企業にもメリットをもたらすでしょう。
クールビズ・ウォームビズの推進
政府は節電対策として、夏はクールビズ、冬はウォームビズを推進しています。
既存の服装規定にとらわれず、季節や体調に合った服を着用することで、オフィスの空調調整を最小限に抑えるのが目的です。
クールビズ・ウォームビズを採用することで、CO2排出量削減、電気代削減などのメリットが得られるでしょう。
まとめ
いま、地球は悲鳴を上げています。
山積みの問題を解決するためには、一人ひとりの心掛けが大切です。
弊社は、事業として「地球温暖化」「海洋プラスチックごみ問題」という2つの環境問題に取り組んでいます。
一人ひとりが”できること”を継続すれば、次第に大きな輪となり、あらゆる環境問題が根本から改善していくはずです。
豊かな環境を次の世代に引き継ぐため、皆で今日からエコ活動を始めましょう。
【参考】
CIALAC(NIKKO)|エコ活動とは|環境を守るために企業と家庭でできる取り組み例を紹介
大同至高株式会社|企業のエコ活動とは?取り組む理由や事例を紹介
Rakuten|海洋プラスチック問題とは?
武蔵村山市|地球温暖化とは?どうなってしまうの?私たちにできること
千葉商科大学|海が汚染され、海の生物も人も危ない! マイクロプラスチック汚染問題とは