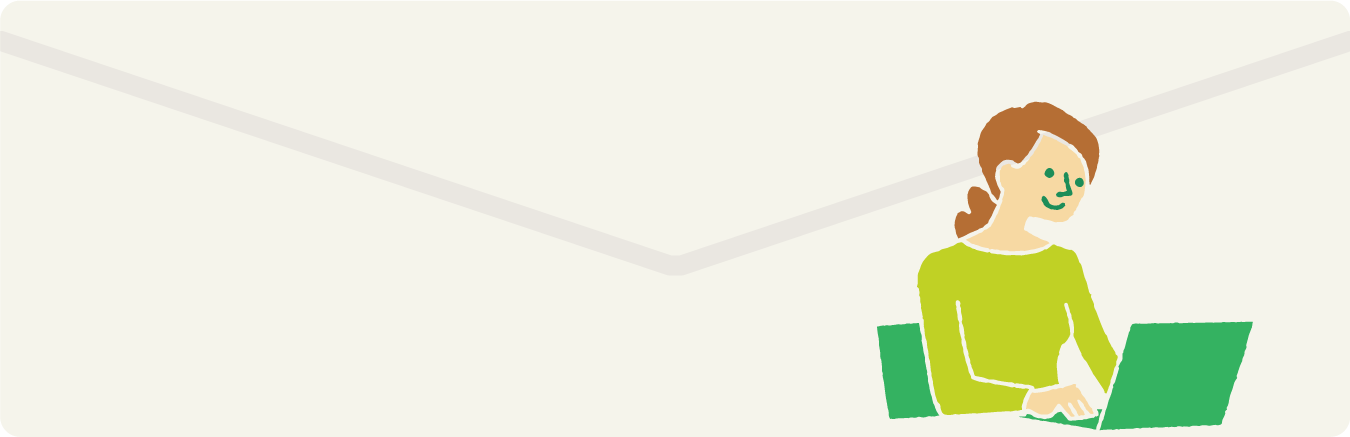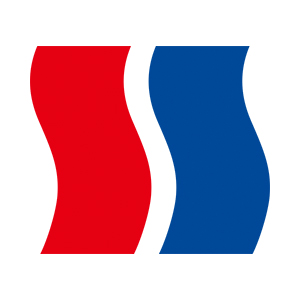環境問題の深刻化が叫ばれる現代。自動車の購入や買い替えを検討している方々は、環境に良いとされる「エコカー」を購入するべきか迷った経験はありませんか?
重い物の運搬、高齢者や子どもとの移動、すぐに出かける必要がある時など、生活のなかで自動車に頼りたい場面は多々あります。私たちの生活を便利にしてくれる自動車ですが、環境への負荷も気になるところ。それを解決してくれるのがエコカーです。
この記事では、環境に優しい車が求められる背景やエコカーの種類と特徴、メリット・デメリットなどについて、分かりやすく説明していきます。
エコカーが求められる背景

エコカーの開発と普及が必要とされる背景にあるのは、地球温暖化やガソリン価格の高騰、エコカー市場における競争の激化などです。ガソリンや軽油などの石油資源を燃料とする、従来の自動車の生産と利用は限界に近づいてきています。
いま世界市場でシェアを拡大しているのは、化石燃料からの脱却に素早く対応したメーカーです。この項目では、エコカーが求められる背景にある環境問題について、関わりが深い点に注目しながら解説していきます。
地球温暖化
エコカーが必要とされる理由の1つ目は、地球温暖化です。近年、地球温暖化にともない、世界各地で猛暑や豪雨、干ばつなどの異常気象の被害が顕著になっています。地球温暖化の主な要因は、二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガスの増加です。
気候変動対策に関する国際的な枠組みであるパリ協定は、気温上昇を産業革命前より1.5℃に抑える努力をすることを目標としています。そのためには、温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、今世紀後半にカーボンニュートラルを実現することが必要です。2021年11月時点で、154の国と1つの地域が2050年までのカーボンニュートラル実現を表明しています。
従来のガソリン車やディーゼル車は、化石燃料を燃焼させることでエネルギーを得るため、多くの二酸化炭素(CO2)を排出し大気中の温室効果ガスを増加させていることが課題です。
日本政府も2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2035年までに新車販売をすべて電動車にする方針を発表しました。このような世界的な流れの中、ガソリン車からエコカーへの移行が進められ、補助金や減税を受けられるなどエコカー購入を促進する動きも活発化してきています。
ガソリン価格の高騰
ガソリン価格の高騰も、エコカーが求められる大きな要因となっています。2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻により、ロシア産の原油供給が制限され世界の原油価格が高騰しました。
また、イランやイラクなどの主要産出国にロシアやメキシコなどの産油国を加えたOPECプラスが原油価格の安定を理由に減産を決定し、供給量が減ることで価格が上昇します。さらに、日本は原油のほぼ100%を輸入に頼っており、円安が長く続いているためにガソリン価格が高止まりしている現状です。
ガソリンなどの燃料費を節約するために、燃費の良いハイブリッド車(HEV・HV)やガソリンを使わない電気自動車(BEV)、燃料電池車(FCV)が注目されるようになりました。自動車メーカーはエコカーの開発・普及に注力し、日本政府も減税や補助金で後押ししています。
このように、ガソリン価格の高騰が家計を圧迫する中で、燃料費を抑えられるエコカーの需要が高まっているのです。今後もエネルギー価格の変動が続く可能性があるため、エコカーの重要性はさらに増していくでしょう。
世界市場での競争力強化
日本の自動車産業が世界市場での競争力を強化するためにも、エコカーが求められています。アメリカの一部の州やイギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、ガソリン車の新車販売を禁止する方針が掲げられています。
近年、世界の自動車市場では電気自動車を中心とした電動化シフトが急速に進んでおり、日本メーカーもこの流れに対応しなければ競争力を失いかねません。
日本の自動車メーカーは、これまでハイブリッド車で世界的な成功を収めてきましたが、電気自動車においては出遅れているとの指摘があります。世界の電気自動車市場では、アメリカや中国、ドイツのメーカーが上位を占めており、日本のメーカーは日産・三菱・ルノー連合が10位と低迷しています。
日本の自動車メーカーもグローバルな競争力を維持・強化するために、エコカーの開発が不可欠です。特に電気自動車分野での出遅れを取り戻すためには、電動化技術の強化、バッテリーの革新、世界市場に適したモデルの投入が求められています。
エコカーは単なる環境対策の手段ではなく、日本の自動車メーカーが世界市場で生き残るための重要な戦略でもあるのです。
エコカーは環境に良い?
エコカーは、化石資源の利用を抑えCO2排出量を削減するほか、大気汚染の原因となる物質の排出を低減した自動車です。
電気自動車はガソリンの燃焼ではなく電力を使って動力を得る仕組みで、燃料電池車は化石燃料の代わりに水素を利用します。また、エンジンと電気モーターを組み合わせて燃費を向上させたハイブリッド車は、ガソリン消費量を抑えることが可能です。ガソリンではなく天然ガスを利用する車種ではCO2排出量が削減され、高機能の処理装置を搭載したクリーンディーゼル車では排気ガス中の汚染物質を低減することができます。
ガソリンなどの化石燃料の使用量を減らせば、主要な温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の削減、燃焼時に発生する大気汚染の原因物質の削減につながります。さらに、国際情勢に左右される石油資源への依存を減らすことは、エネルギー供給の安定性の視点からも重要です。
このようにエコカーは地球環境の保全に貢献し、持続可能な社会の実現に寄与しています。エコカーの種類とそれぞれの特徴については次の項で詳しく解説します。
エコカーの種類と特徴

エコカーの概念には、環境への負荷を低減した車が広く含まれています。CO2排出量削減の面からも、車の構造や使う燃料の違いなどによって多岐にわたる自動車が開発されてきました。
世界のエコカー市場ではメーカー間での競争が激化しており、消費者にとっては選択肢が増えている現状です。この項目では、それぞれの特徴や長所・課題について解説し、エコカーの具体例を紹介します。
電気自動車(EV・BEV)
電気自動車は、バッテリーに蓄えた電力を使ってモーターを駆動する自動車です。化石燃料を燃やさないので、走行中にCO2を排出しません。
さらに、充電に再生可能エネルギー由来の電気を用いることで、走行に関わるCO2排出をゼロとすることができます。また、走行時の静粛性にも優れているほか、部品点数が少なくメンテナンスの負担が軽減される点も長所です。
一方で、充電インフラの不足や充電時間の長さが課題となっています。また、航続距離がガソリン車より短い場合があり、バッテリーの生産や廃棄による環境負荷も無視できません。
日産のリーフは、日本国内で広く販売されており、世界的にも人気のある電気自動車です。また、テスラのモデル3は、航続距離の長さと高速充電機能で評価されています。
\みどりママとエコスケが電気自動車について話します!/
ハイブリッド自動車(HV)
ハイブリッド自動車は、内燃機関(エンジン)と電動機(モーター)の2つの動力源を組み合わせた自動車です。
走行状況に応じてエンジンとモーターを使い分けることで、燃費効率の向上や排出ガスの削減を実現していますが、具体的な削減率は車種や条件によってかなり変動します。モーター走行時はエンジン音がないため、静かな走行が可能です。ただし、複雑なシステムを搭載しているため、ガソリン車よりも自動車の販売価格が高めです。また、バッテリーには寿命があり、10〜15年または走行距離15万〜20万kmが一般的な交換の目安とされています。交換の費用は車種によりますが、20〜30万円程度かかるため負担に感じる場合もあるかもしれません。
トヨタのプリウスは、ハイブリッド自動車の先駆として有名です。ハイブリッド自動車の需要は世界的に高まっており、海外ではフォードのフェスティバやルノーのアルカナなどのラインナップがあります。
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
プラグインハイブリッド自動車は、電気自動車とハイブリッド車の利点を組み合わせた自動車です。ガソリンエンジンと電動モーターの両方を搭載し、外部から充電することができます。
大容量のバッテリーを備えており、日常の短距離移動は電力のみで走行でき、バッテリー残量が少なくなってもエンジンが作動するので長距離の走行も心配いりません。電動モーター走行時は静かでスムーズな加速が特徴で、二酸化炭素(CO2)を排出しません。
複雑なシステムと大容量バッテリーを搭載しているため、一般的なハイブリッド車やガソリン車よりも自動車の販売価格が高価です。外部充電を活用するためには、自宅や公共の充電設備が必要となり、インフラの整備状況によっては不便を感じることがあります。
三菱のアウトランダーは、プラグインハイブリッドの代表的なSUVでオフロード性能もあり悪路走行も得意です。ボルボのXC90 T8は、ラグジュアリーSUVのプラグインハイブリッドモデルで高級感と環境性能を両立させています。
燃料電池自動車(FCV)
燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応によって発電し、その電力でモーターを駆動する自動車です。走行中に排出されるのは水のみで、二酸化炭素(CO2)や有害なガスを排出しません。また、エネルギー効率が高く、静音性にも優れています。さらに、水素の補給時間は約3分と短く、航続距離も長いことが特徴です。
ただし供給する水素について、化石燃料を原料とする場合、製造過程で二酸化炭素(CO2)が排出されます。一方で、製造コストは高いですが、再生可能エネルギー由来の電気を利用し水の電気分解によって製造される水素を供給すれば、水素の製造に関わるCO2排出も削減できます。FCVの課題は、水素の製造や水素を供給するインフラ整備が十分でなく、短期間で普及させることが難しいことです。
トヨタのミライは、日本国内で販売されている代表的な燃料電池車であり、ヒュンダイのNEXO(ネッソ)は1回の充填で820kmの走行可能なSUV※です。
- ※SUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)は、悪路走行性能と実用性を兼ね備えた多目的車という意味で、車のカテゴリ(車両のタイプ)を指し、EVやPHEVなどの分類とは分類の基準が異なります。例としてテスラのモデルY、日産のアリアなどはEVのSUV、上述のトヨタのミライはFCVのSUVです。
天然ガス自動車(NGV)
天然ガス自動車は、基本的にガソリン車やディーゼル車と同じ構造で、圧縮天然ガスを燃料とする自動車です。天然ガスも化石燃料の一つですが、ガソリン車と比較して、CO2排出量を約2〜3割削減できます。また、大気汚染の原因である窒素酸化物や一酸化炭素、炭化水素の排出量も少なく、硫黄酸化物や粒子状物質はほとんど排出しません。
ただし、燃料補給施設の数が限られ利便性に課題があります。また、1回の充填で走行できる距離がガソリン車やディーゼル車と比べて短く、自動車の購入コストもやや高めです。なお、平成30年に施行された排出ガス規制に適合する天然ガス車は、エコカー減税の対象となり重量税が免税となります。
いすゞ自動車は、2021年に国内商用車メーカーとして初となる大型天然ガストラックを発売しました。欧州では、FIATがマーケットリーダーになって乗用車への普及が進んでいます。
クリーンディーゼル車(CDV)
クリーンディーゼル車は、従来のディーゼルエンジンに比べて排出ガス中の有害物質を大幅に低減した自動車です。最新の排出ガス浄化技術を採用し、環境性能を向上させています。
ディーゼルエンジンは回転力が大きく、スムーズで力強い加速が特徴です。また、ガソリンではなく軽油を使うため、1リットルあたりの価格が安く燃料費を削減できます。
高度な排出ガス浄化システムを搭載しているため自動車本体価格が高めになる傾向があり、性能を維持するには定期的なメンテナンスや高品質な燃料の使用が求められます。
なお、廃食用油や菜種油、大豆油などの再生可能資源から作られるバイオディーゼルを燃料とすることも可能です。バイオディーゼルの原料となる植物は成長過程で二酸化炭素(CO2)を吸収するため、燃焼時のCO2排出を相殺できると考えられています。
マツダのCX-5は、クリーンディーゼルエンジンを搭載したSUVです。海外メーカーの例としては、フォルクスワーゲンのゴルフ TDI が挙げられます。
低燃費のガソリン車
「第3のエコカー」といわれる低燃費のガソリン車は、従来に比べて燃費性能を大幅に向上させた自動車です。
エンジンの改良や車体の軽量化、アイドリングストップ機構などの技術革新により、ハイブリッド車並みの燃費を実現しています。燃費が良いためガソリン代が節約でき、車体の軽量化とコンパクトなデザインにより、小回りが利き運転しやすい点が特徴です。
販売価格は電気自動車などに比べて安く、特別な充電設備が不要で従来のガソリン車と同様の利便性を持っています。ただし、軽量化のために車体が小型化され、車内スペースが狭く感じられるかもしれません。
約20〜25km/Lの高い燃費性能を誇るのは、ホンダのフィットです。コンパクトなサイズと扱いやすい走行性能も評価されています。海外メーカーの例は、フォルクスワーゲン・ポロで、燃費はホンダフィットと同レベルです。
なお、政府は2035年までに乗用車の新車販売で電動車100%を実現することを目標にしています。また、東京都の目標はそれより5年早く、2030年までに都内乗用車新車販売台数に占める非ガソリン車の割合を100%にするという内容です。
将来的には、ガソリン車の新車販売は廃止される方向と考えて良いでしょう。
\HV・PHEVなどの英略語の意味をまとめました!/
エコカー購入のメリット・デメリット
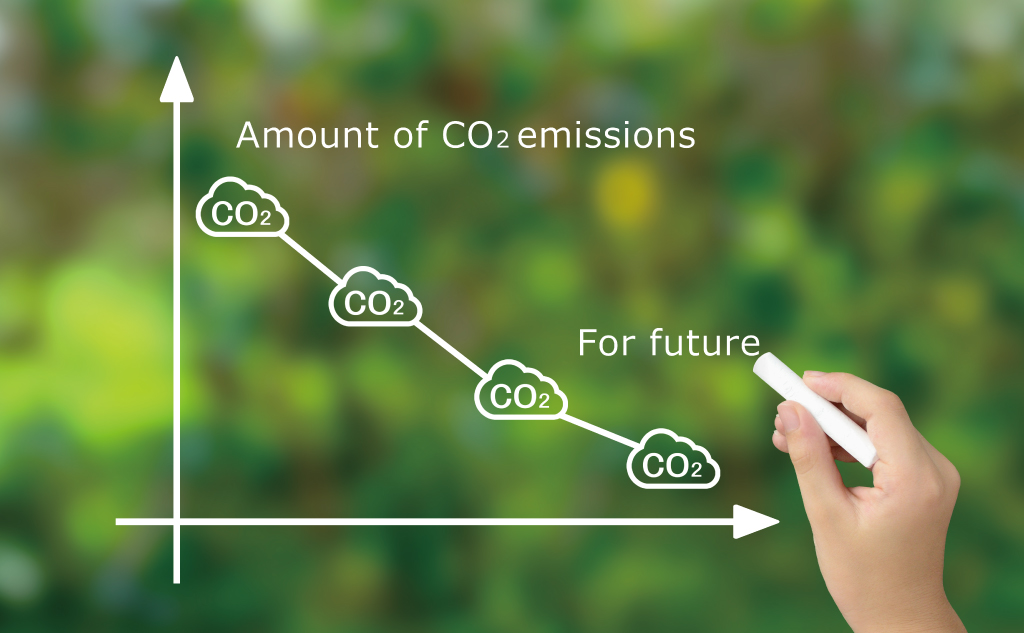
エコカーを選択する最大のメリットは、走行時の二酸化炭素(CO2)の排出と有害物質の放出を削減し地球環境への負荷を減らせることです。ただし、電気自動車やハイブリッド車も、バッテリーも含め製造時には二酸化炭素(CO2)を排出しています。
IEAの試算によると、中型車を15年利用した場合のライフサイクルで排出する1台当たりの温室効果ガスは、二酸化炭素(CO2)換算でガソリン車は54.1トン、PHVは36.9トン、EVは25トンです。燃料由来の温室効果ガス排出はガソリン車が最も多いですが、製造時の排出が一番多いのはPHVとなっています。
また、電気自動車で使用する電気について、発電の際に化石燃料を使用する場合は二酸化炭素(CO2)の排出は避けられません。2022年のデータでは日本の電力発電の約7割を火力発電が占めており、電気自動車も間接的に化石資源に依存しているといえるでしょう。
とはいえ、ガソリンの使用を削減できるのはメリットといえます。ハイブリッド自動車ではガソリンの使用を大幅に節約でき、電気自動車の電気代はガソリン代に比べて安価です。ガソリン代は原油価格の変動に左右されますが、電気代は比較的安定しています。
一方、エコカー購入の初期費用は高めです。また、走行中にエンジンへの切り替えができないエコカーの場合は、燃料の充填場所を考えておく必要があります。
また、電気自動車やプラグインハイブリッド車をフル充電するには何時間もかかるため、その手間をデメリットと感じるかもしれません。
なお、初期費用の負担は補助金や減税措置の利用により、定価よりも安く抑えることが可能です。また、燃料充填や充電のためのインフラ整備にも政府は力を入れており、将来的にはもっと便利になると考えられます。
エコカー減税・補助金

政府は税制優遇措置や補助金によりエコカーの普及を促進しています。
エコカー減税は、電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)・ プラグインハイブリッド自動車の自動車重量税を免税とする制度です。
平成30年排出ガス規制適合のクリーンディーゼル自動車、平成30年排出ガス規制50%低減のガソリン車・LPG車・ハイブリッド車も、燃費性能に応じて減税されます。
グリーン化特例は、電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車・ プラグインハイブリッド自動車の新車新規登録を行った場合に翌年度分の自動車税を軽減するものです。
新車・中古車の購入時にかかる税金については、環境性能割により電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車・ プラグインハイブリッド自動車では非課税となります。また、燃費性能が一定基準を満たす自動車は、税率が軽減されます。
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金は、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車などについて環境性能に応じて支給されるものです。また、充電設備の設置にも補助が適用される場合があります。
補助額や対象条件は年度ごとに見直されるので、最新情報は環境省や経済産業省の公式サイトで確認しましょう。
まとめ
この記事では、エコカーが必要とされる理由やエコカーの種類と特徴、購入するメリット・デメリットなどについて解説しました。地球の未来のために貢献できることや、補助金・減税などの支援、燃料代の削減を考慮すると、エコカーへの初期投資は高くないかもしれません。
自宅のソーラーパネルによって発電した電気を車の充電に利用するなど、移動のためのエネルギーを自給自足することも現実的な選択肢となっています。エコカーの購入について吟味する時間は、生活のなかで何を大切にしたいのか、どんなライフスタイルが理想的なのかを考えるきっかけになるでしょう。
是非、理想の生活を実現してくれるエコカーを探してみてください。
【参考】
経済産業省資源エネルギー庁|電気自動車(EV)は次世代のエネルギー構造を変える?!
経済産業省資源エネルギー庁|クリーンエネルギー自動車の購入補助金がリニューアル、自動車分野のGXをめざせ
東京都環境局|自動車のゼロエミッション化に向けた環境局の取組について
IEA|Data Tools|EV Life Cycle Assessment Calculator
朝日新聞|EU、エンジン車の販売2035年以降も容認へ 全面禁止の方針転換
朝日新聞|テスラ世界販売178万台、初の前年割れ 中国勢との競争激化で
NIKKEI Mobility|世界EVシェア、失速は米・韓・日仏の3陣営 Tesla・BYD上昇